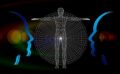これは前回の記事を踏まえての第二弾です。
反差別とインクルージョンが「エリート支配の技術」に変わるとき
近年の日本社会だけでなく、欧米で推進される Critical Race Theory(CRT)やインクルージョン教育は、「多様性」や「反差別」を掲げながら、その実、エリート層の戦略的な道具として機能している側面を否定できない。
ケンタッキー州議員サラ・ストーカーの「白人の子どもたちには、自分の肌の色について悪いと感じる機会が必要だ」という発言は、その象徴的な表現でしょう。
ここで問題なのは、教育が「関係を開く場」ではなく、「特定の子どもたちに罪悪感を刻み込み、身分的な位置を内面化させるプログラム」に変えられていること。
本来、インクルージョンとは、抑圧されてきた声の可視化や発言可能性の拡張を目指すはずだった。だが、エリートが設計し運用する「反差別教育」は、しばしば、白人の子どもたちを“永続的に負債を負う側”に位置づけることで、自らの「道徳的上位性」を保証する道具へと変質した。
そこでは、差別構造に抗する運動そのものが、階級構造を温存・強化するための「規律装置」に転倒してしまう。
近年の日本社会では、「正義」を掲げる運動が、しばしばその内部で逆説的な暴力性を帯びる現象が顕著になっている。象徴的なのは、たとえば以下のような事例もそうでしょう。
東京新聞は11月26日付夕刊のコラム「大波小波」の中で、「伊藤氏を特別な性被害者として神聖化し、告発のためなら多少の人権侵害には目を瞑ってもいいとして擁護する人々も存在する」と指摘。「自分が応援する人や仲間をやみくもに庇い、間違いがあっても見過ごし、批判する人たちを攻撃する仕草は、このところさまざまな場所で見られる危うい現象だ」「カルト的な権威者を作り出すべきではない」と厳しく批判している。 引用元 ➡ 「残念ながら法的な問題は解決されていません」 伊藤詩織さん元代理人がコメント 映画は12日から公開
【「モラハラされた」と訴えていた妻が、実は加害側だったケース】
離婚相談を長くやっていると、
最初にこう言う方がいます。「夫からモラハラを受けていました」
「精神的に追い詰められていました」話を聞く限り、確かに苦しかったのは事実。
ただ、もう一段深く聞いていくと、…— 岡野あつこ®公式 夫婦問題カウンセラー (@okano_atsuko) December 18, 2025
これらの指摘は、単なる個別事例ではない。草津町の冤罪事件に見られたように、告発が「反証不可能な正義」として扱われ、批判者が全否定されたり社会的に抹殺される構造はすでに複数の領域で生じ続けてきました。
その中には草津町の件のようにすぐに事実が明るみに出たケースもあれば、社会的に多くを失ったケースもあれば、自死に至ったケースもあります。
また、特定のフェミニズム運動が左翼系アクティビズムと結びつき、男性一般への憎悪表現や誹謗中傷を公然と行っても問題化されない状況もずっと続いていました。
そういったことの積み重ねによって、「反」の運動が起き、流れはむしろ反の勢いが徐々に優勢になりつつある。
「反」の語りを個々に見ていけば実に粗野で荒っぽいものもあったりすることもよくありますが、しかし大きな流れとして、これもまた弁証法的な流れともいえます。
「完結した正義」こそがカルト化を生み出す。ゆらぎや余白を失った思考は硬直化し、破壊的になり、自滅していく。「反」の運動は「魂の質が異なる本質的な敵」のようにみえるが、「己の魂が生み出した影」でもある。
それを自覚できないまま外部化し、自己正当化を繰り返し続けるとき、「己の影」は分離を強め、徐々にほんとうに「敵」のような姿に強化されていくわけです。
連帯はどこで断罪に反転するのか
連帯が断罪へと反転するのは、関係の生成ではなく位置の固定を目的としはじめる瞬間です。
本来、連帯とは不均衡な関係のなかで声を持たない者の側に立ち、可視性や発言可能性を拡張するための実践。それは連帯する主体自身も関係の変化によって変容し、連帯は常に暫定的で試行的、失敗を含みうるものである。
しかし、連帯が「正しい立場に立っていること」の証明へと変質した瞬間、性格は決定的に変わる。もはや関係を開く運動ではなく、境界線を引く操作となり、「誰が味方か、誰が敵か」「誰が安全か、誰が危険か」を識別する装置へ転化してしまう。
この転化点で連帯は、以下の三つの条件を満たしはじめる。
可視的パフォーマンスの要求:沈黙や逡巡は「不十分な連帯」「隠れた加害性」とみなされ、立場表明の強度が道徳的価値の尺度となる。ここには、バトラー的な「言語行為の強制的反復」が働き、主体は「正しい発話」を繰り返すことでのみ共同体への所属を保証される。
時間的猶予の喪失:理解・学習・修正のプロセスが許容されず、違反は即座に評価・処罰される。アーレントが重視した「熟議の時間」は消滅し、代わりに「即時の正義」が支配する。
免責の付与:正しい側にいる自己認証が手続きや比例性、反省の必要を免除し、断罪を行う主体を批判不可能な位置へ押し上げる。
これはフーコー的な「規律権力の内面化」として理解できます。
この結果、連帯は抑圧に抗する運動であることをやめ、規範遵守を監視する共同体的超自我として機能する。理念の過剰ではなく、安全な位置取りの技術への転化が断罪への反転を生む。
被害者中心主義はどの地点で主権化するのか
被害者中心主義が主権化するのは、被害が語りから権限へ変換される瞬間。
本来、被害者中心主義は、歴史的に無視されてきた苦痛や抑圧を社会的判断の中心に据え直す試みであり、被害は沈黙を破る根拠であり、制度や規範の再検討を促す契機であるけれど、
被害が「反証不可能な正当性」に固定されると構造は変わり、被害は問いを開く契機ではなく、決定を下す権限として扱われる。
ここにはアガンベン的な「例外状態」の論理が働き、被害は法の外部に位置しながら法を決定する力を持つ。この主権化は三段階で進行する。
解釈の最終審級化:「傷ついたと感じた」という主観が、文脈や意図を検討する前に判断を確定させる。ラトゥール的に言えば、経験そのものが「政治化された事実」として扱われる。
時間の停止:過去の行為は更新不能な意味を与えられ、謝罪や修正は「戦略」「自己保身」として無効化される。ここで被害は、アーレントのいう「行為の不可逆性」を絶対化する。
権力としての分配:誰が「本当の被害者」か、誰が「被害者の声を代弁できるか」が争われ、語りは内部序列化を生む。こでは、被害が「資源」として流通し、ハート&ネグリ的な「情動の政治経済」が作動する。
この段階で被害者中心主義は、抑圧への対抗原理ではなく、例外を決定する主権として機能する。重要なのは、被害者自身の意図ではなく、被害が制度や運動の中で媒介される過程で主権的機能を担わされる点。
赦しなき倫理はなぜ快楽的なのか
赦しなき倫理が快楽的である理由は、主体を悩ませずに済む倫理だから。赦しを含む倫理は常に不安定。赦すとは、判断を保留し、行為と主体を完全には一致させず、リスクと責任を伴う行為。
これに対して赦しなき倫理は、主体に明確な役割を与えます。「正しい側に立つ者」「規範を適用する者」「逸脱を指摘する者」という位置は迷いを必要としないのです。
ラカン的にはここで作動するのは超自我であり、「正しくあれ」「告発せよ」「見逃すな」と命令し、主体は従うことで罪悪感から解放され、倫理的快楽を得る。
この快楽は否認されたものであり、「自分は楽しんでいない」という自己理解と結びつくため反省されにくく、制御も困難。
また赦しなき倫理は時間を圧縮します。そして判断は即時、行為は瞬間的に人格へ還元され、遅れや未決定性は悪とされるようになっていく。
結果として、赦しなき倫理はサディズムではなく、形式に忠実で自己を免責するカント的主体が生み出すサド的効果ともいえます。
このように主体は他者を断罪しながら、自らは「正しいことをした」という安心の中に留まるのです。
連帯が断罪に反転し、被害者中心主義が主権化し、赦しなき倫理が快楽化する——これらは別々の逸脱ではなく、すべて、普遍的正しさが媒介を失い、即時に適用される地点で生じる。
そこでは、関係は固定され、時間は閉じられ、主体は役割に還元される。倫理は問いではなく装置となり、政治は未完であることをやめ、「完結した正義」を名乗り始めるようになっていく。
赦しとは、この完結を拒否する力であり、正義が自らを絶対化する瞬間にそれを一度中断する否定的契機である。
だからこの「中断」こそが、連帯が再び連帯でありうる条件、被害が再び語りでありうる条件、倫理が再び思考でありうる条件なのでしょう。
そしてそれが出来なくなった状態が分離肥大化に向かう運動なんですね。赦しなき倫理、断罪の連鎖、被害の主権化、正義の完結、関係の固定、時間の閉塞、主体の役割化、これらが進むと暴力的衝突へ向かう。
そしてシュミット的な「敵の生成」から政治の極限形態に向かうと、それは「殺し合い」になっていく。これはただの理論ではなく、現実に社会は今、全体的にきな臭くなっている。「己の影」に無自覚なまま、「己の正しさ」を絶対化して分離肥大してきたことによって。