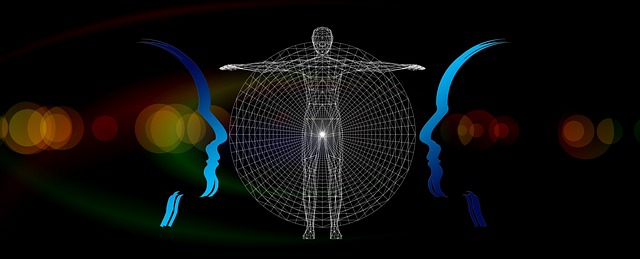今年ラストの記事です。今年は堅い長文の文章が多めでしたが、これは私の思考プロセス及び試行錯誤を含んだ実験的なものでもあるのであしからず。
来年はもっとあそびのある文、余白のある文を書きたいと思います。では少し早いですが、良いお年を。
歌舞伎や能、武道、祭りといった身体文化が再び注目されている。これらは言語に依存せず、身体を通じて直接的な経験を伝える。
現代人が言語疲れや政治的言説への不信感を抱える中で、身体文化は「確かにそこにあるもの」として信頼を取り戻している。
身体は嘘をつかず、共同体的な経験を生み、人の身体(心の基層)に届く。「国宝」のような映画が大ヒットしたのも、現実の背後にある深い流れ(無意識の流れ)のひとつともいえますね。
![]() 一流の文学はつねにそれを九十九匹のそとに見てきた。が、二流の文学はこの一匹をたづねて九十九匹のあひだをうろついてゐる。 福田恆存
一流の文学はつねにそれを九十九匹のそとに見てきた。が、二流の文学はこの一匹をたづねて九十九匹のあひだをうろついてゐる。 福田恆存
一流でなければ駄目、二流は無価値とは思いませんし、そもそも「一流の文学/二流の文学」という区分に特に関心はありませんが、「このスタンスの差異が何を斬り捨てているのか?」ということに関心のウエイトがあります。
共感の政治と「涙の共同体」の限界
身体への回帰は「言語中心主義への無意識的抵抗」であるのと同時に、令和人文のルンペンブルジョワジー化に対し、身体文化は脱実存文学の対極として機能。言語依存の左翼化を超越し、日本独自の生きた伝統を再活性化するともいえます。
今のような時代に、古き文化である歌舞伎、能、武道、祭りなどの身体文化が再注目されるのは、言語中心の現代人文がもたらした疲弊に対する自然な回帰。
言語よりも身体へと向かっている無意識の流れの根底に、身体文化が「九十九匹の言語」を超えて、一匹の実存に直接触れる力をもともと持っていることがあります。
たとえば『人権を創造する』のリン・ハントの捉え方もそうですが、リン・ハントが扱う「身体」とは、想像上で共感される身体、読書によって安全に感受される苦痛、他者の痛みを“見る側”の身体であって、
労働で壊れ、戦争で殺され、責任を引き受けて沈黙する身体ではありません。
つまり彼女の人権生成史は、身体を生きる主体の歴史ではなく、身体を「想像する観察者」の歴史
です。人権が血や汗や義務や失敗の重さからではなく、感情移入という安全圏から立ち上がるものとして描かれている点です。
この枠組みでは、義務として身体を差し出す者、語る余裕を持たない者、苦痛を「物語」にできない者は、最初から視野の外に置かれます。
さらに言えば、『人権を創造する』が前提にしている人権主体は、「読書できる、感情を言語化できる、共感を道徳に変換できる」という意味で、典型的な教養市民=バラモン的人文主体なのです。
共感の政治と「涙の共同体」の限界
ルソーの『新エロイーズ』が生み出したのは普遍的権利ではなく感傷主義的な「涙の共同体」にすぎず、そもそも共感は似た者・美しい者・物語化可能な者・声の大きい者に偏る選別的感情であって普遍的権利の基礎にはなりえず、
人権とは本来、国王の恣意的逮捕や拷問を禁じ、財産権や言論の自由を守るための「国家暴力の制限装置」として成立したものであり、
文学的感情とは無関係であるうえ、「文学が人権を生んだ」という物語は奴隷制・植民地支配・人種差別・労働搾取が続いた近代の暴力を覆い隠す甘美なフィクション。
さらにルソー自身が『社会契約論』で一般意志に従わない者を「自由になることを強制される」と述べたように人権の普遍性を否定する全体主義的契機を含んでいることを踏まえれば、
「人権=物語への共感」という説明は、①人権の起源を感情に還元し、②法思想史を無視し、③共感を普遍倫理と誤解し、④近代の暴力をロマン化し、⑤ルソーの政治思想の暴力性を見落とすという複合的誤謬から成る、歴史的にも思想的にも誤った近代の自己神話にすぎない。
「共感主義的ヒューマニズム」は本質的に偏っているもので、それに従う姿勢こそ、むしろ内外化された非対称性をより深く見落とすことになる。
特に「言語化された物語」に偏る者たちは、物語化できる者、声の大きい者、そして「政治性(価値観)が似た者」、語りやすい者(感じの良さ)といった、「九十九匹」には共感が多く向けられるが、
言語化できない、得意としない者、苦悩が不可視化され語ること自体をよしとされない者、といった「声を持たない者」は“共感したい人間”として数えられない。
つまり、共感を基礎にした人権論は、そして「涙の共同体」は最初から“一匹”を排除する構造を持つ。
不可視化された負担とジェンダー言説の盲点
フェミニズムが女性の負担を構造的問題として可視化する一方で、男性が歴史的に担ってきた経済的責任・家族維持義務・法的責任・社会的制裁リスク・戦争動員や危険労働の強制・家族失敗の全責任といった重い負担を「義務」「美徳」「責任」「特権」として再符号化し分析対象から排除した結果、
本来は権限と引き換えに義務・犠牲・制裁・破滅リスクを男性に集中させることで成立していた“男性の犠牲を制度化した家父長制”が「男性の一方的支配」として単純化され、
現代ジェンダー論では女性の負担が構造化されるのに対し男性の負担は個人責任へと還元される二重基準が固定化し、制度化された義務の当然視・犠牲の美徳化・男性失敗の人格化・「男性=加害者/女性=被害者」という道徳的物語の政治的維持によって、
男性の負担・犠牲・義務・リスクは体系的に不可視化され続けてきたのである。
まずこのマクロな流れがあり、その上にさらに個々の実存的な苦悩がある。それは二重に不可視化された「声なき実存」。一匹とはそのような不可視化された者たちを含む。
現代を覆い尽くすフェミニズムや多様性、ジェンダー思想といったリベラルな視点、そういった「思想の強さ」が反映された「涙の共同体」の大きな共感物語は世に蔓延り、本屋にズラっと横並びしている。
「九十九匹の正しさ」は政治的正義であり、「一匹の正しさ」は文学的・実存的な善である。そういった大きな政治的正義(九十九匹)の中に馴染まず、あるいはその外を生きる者、そういった「リベラル言説の外側にあるもの」にスポットを当てる、そういう文学の底力、身体性がどんどん失われていった。
女性の負担だけを構造化し、男性の負担を個人責任に還元し、「男性=加害者/女性=被害者」という物語を維持し、男性の犠牲・義務・リスクを不可視化するという 政治的言語の構造、
これは福田が批判した「政治の言葉で文学を語る(=政治的正義が人間を裁く)」という構造と同じ。
つまり、現代のジェンダー言説は、九十九匹の政治的正義の側に立ち、一匹(不可視化された者たち)を見ようとしない。
文学の脱実存化と身体性の喪失
人文系学問の左傾化とルンペンブルジョワジー化は、戦後イデオロギー主導の脱実存化を招き、令和期の文学に抽象的情緒主義を植え付けています。
この結果、小説は身体性・実存を失い、読者(群れから外れた1匹)の「実存」に届かず、自己言及的な空回りに陥っています。
人文系はマルクス主義・ポストコロニアル論で「抑圧の物語」を優先し、普遍的人間性を解体。思想力の衰退後、消費文化に適応したルンペンブルジョワジー化が進み、文学もアイデンティティ政治の道具化を強いられました。
ドストエフスキーやカフカのような実存文学は肉体苦痛・生の危機を描きましたが、現代小説はSNS的共感や「多様性」表象に終始。
心の深層や身体的実感を避け、表層的「物語化」しか生み出せません。この脱実存化は、福田恆存の「一流文学は失せたる一匹を探す」精神を欠き、二流のうろつきに堕す。
身体性の喪失した文学、小説は、「それ自体を生きる人々」の「心」には触れず「実存」に触れることもない。読者の「心」に触れぬ文学は、自己美化の鏡となり、文化の活力源を断絶させていく。
それは、その作用を真に受けた人々も同様に。 そうやって人文と制度の中で心を扱う人々の言説の権力、権威性が、「実存」をその「(深いつもりの)知的な言語」で漂泊していく。
専門家の閉鎖性と「一匹」の排除
現代は個人主義的にマイペースに生きることは昔よりずっと楽。殊更「変人」であることを気にする必要はなく、「自称:変人」もいわゆる「ファッション変人」みたいな感じで、全く本来的な不器用さがなく異質性を感じない。
昔の変人はそれしかできなかった不器用人。「こういう風に生きてもいいんじゃない?」的な「選択」を他者に問えるような器用で適応的なキラキラした「自称:変人」ではなく、もっと宿命的で、極めて実存的な不格好な者。
人文アカデミア的な「人間中心主義の自己完結性」は、不可解さ・他者性・非人間性を本質とする妖怪的/漫画的感性に対して、質的に最も遠い極の一つ。
「人間」の「外」に排斥された存在が「妖怪」、その根源的な実存的疎外それ自体を生きることもなく、「異能」や「マイノリティ」にのみフォーカスする「自称:妖怪」は、「似て非なる人間の言葉」で埋め尽くすことで世界から妖怪の実存を排斥する。
妖怪が生きている場所(外・裂け目・不整合)に彼ら・彼女たちが触れることはない。「実存」はそうやって排除される。
このように「それ自体を生きる者」は「似て非なる者」によって場から排除され、「非人間」のように扱われる。しかし「非人間」のように扱われる一匹にさえ届くものというのは、「自称:変人」「自称:妖怪」の言葉ではない。
「多様性の肯定」が同時に「本来的な差異の消去装置」になるもまた、同じ構造なんですね。差異は言語化されると同時に統治的に調整され、結果的にその“生”そのものから切り離される。
その切り離された差異は、しばしば“管理可能な多様性”へと転換される。ほんらい、「差異」には言語化/制度化できない「生」がある。
「理性・言語・制度」の範囲で規定される「人間」というものは「全体性を失った人間」です。しかしある種の「人間(我々こそ人間と思い込んでいる人々)」たちが、人間から「差異」の身体性を(無自覚に)スポイルしている、ということ。
アカデミアや思想界でも、“全体性としての人間”——つまり、理性・感性・身体性・霊性の統合体——が欠落し、部分的な人間像(制度的・理性的・文化資本的)を“人間の標準”として再生産している。
こうして「全体性としての人間」は減っていき、「半人前の人間」があたかも「これが人間なんだ」と“思い込む”ようになっていく。そういった「半人前の人間」が「人間」を定義したがる不毛な現象は昨今の一部の人文アカデミア、学者、専門家、知識人に目立つ。
Jリベラルの構造的盲点
欧米リベラルの影響を強く受けたJリベラル(ほんとうの意味でのリベラルではない者たち)は差別や排除をなくすために言語を整備しようとする。
しかしその過程で、曖昧さ・矛盾・弱さ・不器用さ・実存的な揺れといった“人間の生の部分”が排除されていく。これはまさに、「安全な言語空間」を作るために、“危険だが豊かな人間性”を排除する運動。
不快なもの、危険なものを消す、異論を消す、あらゆるグレーゾーンを消す、しかしその結果、深さ・複雑さ・矛盾・実存の重さといった“生の厚み”まで消えてしまう。
これは「言語の衛生化」が「人間の非衛生的な豊かさ」を奪うという、典型的な近代的パラドックス。
Jリベラルは「差別を定義し、批判する側」に立つことで、誰が差別者で、誰が被差別者かを決める権限を事実上握ってきた。これは制度的権力ではなく、言説空間の権力。
この権力を握った瞬間、彼ら自身が行う排除は「正義のための排除」として不可視化される。
Jリベラルは「定義された差別」を批判しながら、もっとも“文化的に洗練された排除”を行っていることに無自覚なまま、そして他者の実存の厚みを疎外していることに無自覚なまま、「排外主義」を批判する。
Jリベラルは己自身が「共感による排除」を行ってきた、行っていることに無自覚。共感の政治を掲げながら、「共感の偏り」によって他者の実存を切り捨ててきた。
昭和から令和まで時代の流れを体感しつつ見てきて、「クリーンで、(一面的には)正しくて、整備されていて、しかしどこか息ができない世界」をリベラルは生み出してきたといえる。
Jリベラルは「己が嫌いなもの、汚いと感じるもの、不快と感じるもの、悪と感じるもの」をグレーゾーンを含めて徹底的に排除しながら「多様性」を語り、「排外主義」を批判してきた。
まさに己自身が他者に対してそうしてきたにもかかわらず「こんな世界に誰がした!」と上から目線で啓蒙したがる。
Jリベラルにとって「排外主義」は、もっとも分かりやすく、もっとも安全に、もっとも道徳的優位に立てるテーマ。そして排外主義の被害者像は、Jリベラルが共感しやすい“弱者像”と一致する。
敵役が明確、善悪の線引きが簡単、自分たちの立場が“絶対善”として確保される、複雑な実存や歴史的負荷を考えなくていい。
まさに「九十九匹の正しさ」に直結することで道徳的に優位に立ちつつ、排外主義を批判することで、自分たちの排除(文化的・言語的・共感的排除)を“見えなくする”。
そうやって外向きの排外主義だけを悪魔化し、内向きの実存的排除を不可視化する。
どのように“文化的に洗練された排除”を行っているかを自覚しないまま、「異なるものを受け入れよう」と語るJ リベラルの構造的な盲点が、他者からの不信や嫌悪を生み、結果的に分断を深める。
そして皮肉な結果として、J リベラルが排除した「生の厚み」を別の場所が回収してしまう。「己の影」を見ようともせず、己を常に正しい側に置いて問題を外部化して正当化し続けるゆえに、「影」は明確に実体のある運動として現象化していく。
制度化された心のケアの限界と「内集団の共栄圏」
人文系・臨床系の領域は、扱うテーマの性質上、特定の価値観と親和性が高く、同じ前提を共有する人々が集まりやすい。
そこにSNSの仕組みが加わることで、異論が入りにくく、入ってもブロックすればいいだけで、結果的に同じ価値観の者たちからの称賛・共感がメインに増幅される環境が構築される。
結果として、専門家自身が「自分はわかっている側」にいるという自己イメージを強め、様々な批判に含まれる「個々の身体性、実存的な濃淡」を感じ取ることもなく、一律に攻撃や難癖とみなし、群れ(内集団)の外部の声を聴く力を失っていく。
「己と内集団の痛み」には非常に敏感で、共感し合い庇い合い応援し合うが、共感の「外」を生きる他者の生の厚み、痛みには気づきもしない。そうやって強迫観念的な自己防衛とプライドの維持だけが最優先される。
それに加えて、承認の市場 → 経済的インセンティブ(著書・講演) → メディア露出 (大手メディアからの記事依頼)は金銭的報酬へとつながり、
この状況、つまり専門家としてのブランド(市場的価値)や社会的評価を維持することが優先されていく中で、「批判的に聴く力」よりも「支持を維持する力」が優先され、結果的に内集団バイアスや利害のバリアがより強化されていく。
その結果、もはや「九十九匹の正しさ」しか扱えず、不可視化された実存(一匹)になど目もくれない存在となって「内集団の共栄圏」に閉じていくわけです。これはバラモン左翼も構造的に似ていていますね。
残念なのは、心の専門家とか小説に関わる人たちが「ああ、こういう感じなのか」と感じることが増えてきたこと。「本をたくさん読む人は今の時代こういう感じになるのか」というのもSNSでは可視化されている。
SNSでの発信をたまにみているだけでも、「これじゃますます群れからはぐれた一匹たちは遠ざかるだろうなぁ」と感じる専門家や人文系、小説家?も多いのだから、もっと思想の強い人々は、さらにそういう感じが強化されているのでしょう。
日本のカウンセリング利用率は、主要国の中で“圧倒的に低い(欧米の1/5〜1/10程度)。カウンセリングの利用率が極端に低いこともそうだが、それは心を扱うはずの領域が、心から最も遠い場所になってしまっているから。
そしてこれを単に「制度が弱いから」では説明するのは単純化であり、制度が弱いのは、人々が“制度化された心のケア”を求めていないから。
心の専門家への不信、言語の内輪化、政治性の強さ、実存への非到達性、これを制度化で補おうとしても、それこそ生権力の一種にしかならない。
人々が求めていないものを専門家が制度化すれば、それはケアではなく統治になる。人々は望んでいない、実存はそれを求めていない、それゆえの結果であることを受け止めるのが先。
これは単なる文学論ではなく、「誰に向けて語るのか」という倫理の問題であり、
リベラル、左翼の運動が何故相手にされないのか?そして人文系の閉鎖性、内輪化、SNS等での自己強化、そして「群れの外」にいる人への非到達性というすべての問題に通底している。
「一匹」は群れの外にいる。つまり、内輪の言語では届かず、内輪の価値観では届かず、内輪のネットワークでも、内輪の政治性でも届かない。
では誰が「一匹」に届くのか。それは、群れの外に立つ者、内輪の安全圏に依存しない者、自分の正しさに酔わない者、孤独の経験を引き受けている者、言語の閉鎖性を自覚している者、そして身体性・実在性を重んじる者。