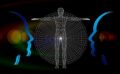あけましておめでとうございます。
今年は昨年の残りの下書き記事を幾つか仕上げて投稿します。春以降は昨年扱っていたテーマと少し異なる方向に移行していくと思いますが、今年もゆっくりマイペースに書いていきます。
ではここで一曲紹介。安里屋ユンタ(新安里屋ゆんた)沖縄民謡です。
ケアとは、一般的に言えば、「他者が生きる力を保ち、回復し、成長することを支えるために、その生活や身体、感情、関係の条件に働きかけ、必要な負担を引き受ける実践」と考えられます。
この定義は、ケアをただの優しさや道徳心と捉える考え方を超え、社会的・実践的・制度的な側面を含めた包括的な概念として位置づけています。
ケアは感じられる前に引き受けられ、もし失敗すれば命や生活に直結する重大な行為であり、その重要性は「気持ち」の有無だけに依存しません。
ところが近代以降の議論、特にフェミニズムやケア倫理学の流れでは、ケアはしばしば「共感」「情緒的な反応」「人間関係の維持」といった感情や関係性の側面に強く注目されてきました。
マーサ・ヌスバウムが指摘するように、感情は倫理的判断にとって重要ですが、本質的に偏りやすく、不安定であり、制度や普遍的規範の基盤としては脆い面があります。
共感は似た状況の人や語れる人、苦痛が可視化されている人に向きやすく、沈黙している人や危険を引き受ける人は見過ごされがちです。
このような感情中心の理解は、歴史的に男性が担ってきた「危険や責任を引き受けるケア」を見えにくくしてきました。戦争や防衛、稼ぐ責任、法的・社会的制裁、失敗したときの全面的な責任など、男性が引き受けてきた負担は、ケアの語彙の外側に追いやられてきたのです。
ケアと倫理:感情倫理の限界
キャロル・ギリガンがコールバーグの倫理段階論を批判した際に示した「関係の倫理」は、人間的関与を倫理の中心に置いた重要な転換でした。
しかしそれが感情倫理として独立的に展開すると、制度や権力配置、社会的リスクの分担といった構造次元が後景化します。
ナンシー・フレイザーが指摘するように、ケアを倫理や承認の問題だけに還元すると、労働やリスク、経済構造など政治経済的な側面が見えなくなり、ケアが「感じる能力」や「関係性の質」へと過剰に道徳化されてしまいます。
結果として、「感じないケア」「語られないケア」「失敗すれば命に関わるケア」が倫理的言語の外部に追いやられる。この現象こそ、感情倫理が生み出す不可視化の構造的問題です。
この不可視化は、倫理理論の水準にとどまらず、現代の心理学、とりわけ臨床心理学の知の形成条件そのものにも深く関わっています。
臨床心理学と労働経験の断絶
心理学者や臨床家の多くは、一次産業や二次産業、ブルーカラー労働に典型的に含まれるような、危険を伴う身体作業や、失敗すれば即座に生活や生命に影響が及ぶような継続的実践の経験をほとんど持っていません。
ここで、シモーヌ・ヴェイユ「工場日記」に関連する外部サイト記事の紹介です。
工場にとどまり、だれの眼にも、自分の眼にも、無名の大衆といっしょくたになっているうちに、他の人びとの不幸がわたしの肉と魂に入りこんできました。わたしと不幸を隔てるものは皆無でした。わたしはほんとうに自分の過去を忘れさり、どんな未来も期待していませんでした。当時の疲労をのりこえて、なお生きのびられようとはとうてい思えなかったからです。工場でこうむったものは、わたしにいつまでも消えない印を刻みつけたので、いまでも、相手がだれにせよ、どういう状況にせよ、だれかに横柄でない態度で話しかけられると、それはなにかのまちがいであり、そのまちがいは残念ながらすぐにも訂正されるだろう、と思わずにはいられません。わたしはあそこで生涯消えることのない奴隷の烙印をうけたのです。 引用元 ➡ 労働の霊性を求めて。精緻な記録に校閲を加えた決定版 シモーヌ・ヴェイユ『工場日記』 冨原眞弓訳 佐藤紀子解説
◇ 関連外部サイト記事の紹介
ヴェイユが生きた時代の工場労働者の多くは男性でした。工場での労働よりも鉱山、建設、農業等、もっと過酷な現場がありましたが、重労働や危険を伴う仕事などは、基本的に男性が担っていたのは今も当時も同じです。
ヴェイユ自身が工場での労働を経験した際、彼女の目に映ったのは、肉体的に過酷な労働を強いられている男性たちの姿でした。
とはいえヴェイユのルノー工場での作業は、主に部品加工やプレス・フライス工程を中心とした比較的軽めの組立・加工作業でした。しかも滞在期間は短期(約2ヶ月間)。
米国労働統計局(BLS, 2023)によれば、職場における致命的労働災害の約90%以上は、建設、製造、運輸、農林漁業といった身体的リスクの高い産業に集中しており、
建設業や農林漁業における死亡災害率は、教育・医療・専門職サービス分野と比較して数倍から十倍以上高い水準にあります。
EU統計局(Eurostat, 2021)でも同様の傾向が確認されており、致命的労働災害の約93%が男性に集中し、その大半が肉体労働・危険労働を含む産業部門で発生しています。
日本においても厚生労働省の統計は、建設業、製造業、運輸業、消防・自衛関連職において、死亡・重篤災害が顕著に集中していることを示し続けています。
一方で、心理学者・臨床家の典型的なキャリアパスは、高等教育機関を中心とした知的労働・対人援助職に限定されており、中小企業や現場労働における、代替不能性の高い責任や、身体を酷使しながら引き受けざるをえないリスクへの長期的参与は、制度的にほぼ排除されています。
この構造的隔たりは、心理学的知が、語りうる経験、内省可能な感情、言語化できる関係性を中心に編成されやすいことを意味します。
シモーヌ・ヴェイユと工場労働者の視点
ヴェイユの「工場日記」のような労働者の一面的な理解の仕方は、人(主に男性)によっては決めつけ的な思考にも思えるかもしれません。しかし比較的軽度な短期の工場作業とはいえインテリ女性にしてはよく頑張ったとはいえます。
しかし、繊細でないと気づけないことも確かにあるけれど、脆弱で繊細だけだと、「場」に圧倒されて、「場」にはその先があること、奥行や広がりがあることがわからなくなることがある。
たとえば「学知だけの人」の中には、「人は大学に行かないと人生は地獄」と本気で思っている人もいたりするが、そういうインテリの言説こそが生の多層性を見えなくしていることがある。
まず重要なのは、ヴェイユ自身の立場です。彼女は思想的・倫理的動機から自発的に工場へ入った。身体労働に慣れていない知識人女性が「理解」するために身を投じるという「自己犠牲的・宗教的志向のフィールドワーク」ともいえます。
このような短期体験型のインテリの言説のよくある見落としは、フィールドワークは必ずしも身体性を豊かにはしない、ということ。
労働史家のエドワード・P・トンプソンや、フランス社会史(Alain Cottereau など)が指摘するように、このような立場の人間は、工場を「生活の場」ではなく倫理的極限状況として経験しやすい。
脆弱な状態であるときは「根」にばかり拘る。立っているのがやっとだから。でも「知」で理解するのではなく、身体が「場」に立てるようになると、もっと別の視界が開けてくるが、インテリ女性にはやはり酷だったようだ。
彼女の思想はある面はとても深いが、「男たちが背負っているもの」は彼女には重すぎて深刻になり過ぎてしまって、「重力」にばかり囚われてしまって、「場」の別の可能性を失っているという両義性が見落とされています。
当時、製造業では女性は繊維・軽組立に、男性は鋳造・溶接・重機械といった過酷な核心工程に集中したように、同じ工場経験や労働の現場においても部署や役割の担当は性差で分けられている。
この分業が男性労働文化の「厚み」を形成し、短期的観察者(ヴェイユを含む)には捉えにくい両義性を生みます。
「何かの厚みゆえに何かを見落とす薄さ」、「何かの深さゆえに何かを見落とす浅さ」、「厚みと薄さ、深さと薄さが同時にある」、この両義性が人間の全体性。
女性や非力な男性にとっては、リアルな「奴隷感覚」となるような「重力」を、多くの男性は「労働」として黙々と背負ってきた一面がある。そして、その上でさらに「自分よりも弱い他者」を養い、「責任」という重力までも引き受けてきた一面も。
1930年代の男性工場労働者の記録(フランス自伝、イギリスMass Observation、労働組合誌)では、「工場は地獄だが俺たちの場所」「疲労や危険は慣れ・勘・腕で切り抜ける」「機械や仲間への誇り、監督への反感と内部連帯」といった語りが見られます。
だから自分を「奴隷」とはせず、「危険を引き受ける者」として認識し、鉱山や軍隊経験世代では工場労働を「比較的扱いやすい地獄の一つ」と捉える語りもありました。
ヴェイユにとっては限界体験であった「短期の工場労働」も、男性労働者にとっては連続した人生の一局面でした。
「誰か」がそれを引き受けているから生活や日常が支えられているし、「誰か」がそれを避けても、それらの仕事は「誰か」がやらなければならない。
「弱さ」「被害」「抑圧」「傷つき」の方向性で言語化したところで男の仕事、現場、役割がなくなるわけではない。だから男はそれを「腕を上げる」「タフさ」の方向性で語りつつも、
徐々に技術を進歩させ、負担を減らし、現実の中でレベルを底上げしながら「全体」を考えて解決しようとする。ここには「持ち場を引き受ける自己実現」が存在します。
一般的な個人レベルの「自己実現」は、やりたいことを選ぶ、自分らしさを追求する、好きな仕事で輝く、といった選択可能性の豊かさを前提にします。
しかし、 「持ち場における自己実現」は、「ここは俺の持ち場だ」「ここは任せろ」という引き受けから生じる。
この構造は、社会的・労働的に誰かが引き受けなければならないものであり、その成立の仕組み自体が『男性の弱さ』や『男性の被害』の言語化を前提としていないのであって、男性個人が弱さを意識的に排除しているわけではない。
「インテリによる短期的参与&観察に基づく記述」は、一面では深い洞察を示すものの、男たちが背負う『生の厚み』には触れきれない。なぜなら、最終的にはそれを身体で引き受けるのは現場の男性自身だからである。
ヴェイユに限らず、学者やインテリが社会の厳しい現実をどれだけ深く「理解」しても、実際に「そこに身を置き続けて生活している人々の体験」を再現することはできない。
現代において重要なのは、このような視点がケア倫理にどのような影響を与えるかという点です。特に、ケアを「感じること」や「共感」のみで語る場合、むしろ他者が黙って引き受ける苦しみや負担を不可視化してしまうのです。
知の権威化の二重構造(身体経験+価値基準)
臨床心理学が「言葉」を主要な媒介とする実践であること自体は否定されるべきではありません。しかし、身体を賭けた責任引受や、危険と隣り合わせの労働がもたらす実存的厚みが、知の形成条件から欠落しているとき、心理学は人間の生を部分的にしか捉えられなくなります。
とりわけ、「男性の身体性」に固有の、消耗、故障、沈黙、壊れやすさ、代替不可能性といった側面は、感情語彙や内省モデルの外部に置かれやすく、その結果、心理学的理解の中で不可視化されてきました。
これは男性個人の問題ではなく、「心理」、「精神」における専門知や制度が、どのような身体経験を前提とした人々によって構築されてきたのかという、認識論的な問題です。
さらにその「知」の価値やその「外」を生きる「他者」への評価基準も、特定層の社会文化的経験 に基づいている。
この身体知の偏りは、ケアを「感じる能力」や「語れる関係性」に還元する感情倫理の構造と相互に補強し合い、結果として、引き受けるケアの実存的現実を理論的にも臨床的にも周縁化してきたのです。
ケアの倫理と産業構造
近代以前の社会では、インフラの維持や生産、運搬、防衛、治安維持などは、体力を要し、常にリスクを伴う仕事でした。これらは社会の存続に欠かせない活動でした。死亡率や事故率も男性に集中していました。
戦争でも、男性は前線や長期駐屯など高リスクの任務を担い、失敗すれば共同体の生存に直結することも多かったのです。
こうした条件下では、身体的特性と社会的役割が結びつき、危険や責任を男性が引き受ける「中動態的帰結」が生じました。
中動態的帰結とは、能動/受動の二分法では捉えられない、環境条件・技術条件・身体的制約が相互作用して形成される役割分担を指します。 つまり、男性が危険負担を担ってきたのは、単なる支配意志や文化的規範ではなく、
また、制度としての形ばかりに注目するのではなく、当時の時代的・技術的条件のもとで人々が相互補完的に生活を成り立たせようとした戦略が前提にあったことを理解すべきです。
技術の進歩やインフラの整備でその制約が徐々に解体されていく中で、中動態的帰結を能動的な支配として「悪意的」に再解釈して、「加害/被害」の文脈に回収することで、男女双方の営みの多義性や両義性を削ぎ落して単純化してしまったのです。
この構造は、産業化の進展とともに新たな形で再編されました。機械化・大規模生産・官僚制の発展は、生産と再生産の分離を制度化し、家庭と労働の二極に社会を分割しました。
女性は「感情労働の担い手」として家庭内・ケア産業へ、男性は「危険労働・責任労働の担い手」として産業・防衛・管理領域へ割り当てられ、この構造がケア概念の再定義を方向づけました。
つまり、ケアの公共的・物質的側面は「仕事」として切り離され、感情的・関係的側面のみが「ケア」として認識されるようになったのです。
近代国家と性別分業による「ケアの再定義」は、産業構造の発展そのものと不可分です。経済が効率性と安全性を最優先するほど、リスクを引き受ける行為は不可視化されやすくなる。
結果として、「失敗しない限り可視化されないケア」が社会の基盤を支えているにもかかわらず、評価も承認も与えられません。
男性的ケアが見えにくくなる理由
定義レベルでの縮減:ケアを「共感や配慮、情緒的な世話」と定義すると、危険やリスク、責任を引き受ける行為は除外されます。
可視性の非対称:家庭内ケアは見えやすく記録されやすいですが、防衛やインフラ維持、労働災害などの「うまくいった」行為は「問題が起きなかった」と見なされ、目立たなくなります。
解釈枠組みの政治化:歴史や産業構造を無視し、役割分担を単なる「支配・権力」の結果として語ると、男性の負担は固定化され、批判なしに受け入れられます。
感じるケア:共感・配慮・関係性の維持、身体的・情緒的な世話 → 家庭や親密圏で可視化されやすい
引き受けるケア:危険・失敗・責任を引き受ける、防衛・稼得・インフラ維持・危険負担 → 成功している限り見えにくいのは、その多くが家庭や親密圏の外、公的・職業的領域で行われるため、日常の感情的ケアのように直接「感じられず」、可視化されにくい
どちらも他者の生活や生存を支えるケアであり、一方だけを倫理化し、もう一方を権力や支配として読み替えることは、ケア概念を狭めてしまうことにつながります。
両者は対立するものではなく、人の生存条件を支える相互補完的な実践です。 ケアとは、感じることだけではありません。生き延びさせるために、黙って引き受けることでもあります。
この両義性を回復しない限り、ケア倫理は、人間社会を成立させてきた実践の半分しか語っていないのです。