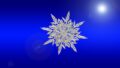今日は、「あれが真理!、いやこれこそが真理!」と人はいろいろ言うけれど、「そもそも真理とは何ぞや?」ということと、「無知の知」のテーマの続き、補足的な考察記事を書きました。
ではまず一曲です♪ 先月のTEPPENの「芸能界ピアノ女王ランキング」で優勝した「ハラミちゃん」の演奏は、躍動感とエナジーが凄く伝わってきました。
では本題ですが、先に「真理」という言葉の定義、意味から入りますね。
「Oxford Languages」
本当の事。間違いでない道理。正当な知識内容。判断内容がもつ客観妥当性。意味のある命題が事実に合うこと。論理の法則にかなっているという、形式的な正しさ。「Wikipedia」
真理(しんり、希: ἀλήθεια、羅: veritas、英: truth、仏:vérité、独: Wahrheit)は、確実な根拠によって本当であると認められたこと。ありのまま誤りなく認識されたことのあり方。真実とも。
この定義と意味範囲では、たとえば宗教の教義とか聖典とか、霊的な本とかは、客観妥当性や事実性が明確に確証されたわけではないし、「間違いでない道理」「本当の事」と断定できる性質のものではないんですね。
その手のものは「信仰」が決定するだけなんです。「それを信じる人」が、「それは真理である」と「思う」「感じる」だけであって、
そのこと自体は自由ですが、それが真実かどうかは客観的に証明はされていない、「わからない」が原則なんですね。なので普遍的な真理とはいえない、ということです。
![]() 現実はその根底において、 常に簡単な法則に従って 動いているのである。 達人のみがそれを洞察する。(湯川秀樹)
現実はその根底において、 常に簡単な法則に従って 動いているのである。 達人のみがそれを洞察する。(湯川秀樹)
ただ、プラグマティズム的に真理を解釈するのであれば、「人間にとって」の普遍的な有用性から「○○は真理である」と、限定的に言うことは出来るでしょう。しかしその本質は「相対的なもの」にとどまります。
ヒトとニンゲン、というテーマで「ニンゲンは概念しか認識できなくなった」と書いたのは、ニンゲンの本質であり、「ニンゲン意識は普遍的真理を知りえない」ということなんですね。
〇 人は”概念の囚人”である。脳は生存のために現実の断片のみを認識する
人間は、「実」にはとどまれない弱さ(脆弱さ)を有するがゆえに、過剰なゆらぎが生じ「虚」を生み出し続け、「虚の世界」の中で生きる創造的存在であり、
ニンゲンは、「概念・観念と同化一体化した虚体」でありつつも、「実体であるイキモノ性」を超え、遥かに複雑な運動性を生み出す中心力となっています。
「ニンゲンが語る真理」というものは、普遍的ではない虚であり観念に過ぎないが、それは普遍的な真理よりも人間精神にとっては強く作用し、
その作用の質、力関係を見るなら、「隠れている普遍的な真理よりも実体的である」といえるため、その意味において普遍的、という多重の意味・構造を持っています。
哲学に、「アプリオリな判断」と「アポステリオリな判断」という概念があり、「判断」にも「分析判断」と「総合判断」がありますが、その捉え方は多元的です。
フィヒテによれば、アプリオリな判断は、原則から推論によって導出されたものであり、アポステリオリな判断は、「推論と経験が一致した場合に、経験において与えられている」判断である。
アプリオリ(演繹的証明の必要のない自明的な事柄)な意味での普遍的真理が存在するか?といえば、「存在しない」というより、「未知」として何かが背後に存在するとしても、それを常に知りえない。
素朴実在論が日常的には絶対普遍に感じられても、また反対に独我論や観念論が絶対普遍に感じられたとしても、「いや科学的実在論こそが絶対普遍だ」と感じられたとしても、
「根源的な前提それ自体」のさらに根源の「未知」は残り続け、「全ての未知がもはやない」という絶対普遍の真理というものを人は知りえない。
「未知」は「未だ知られていないもの」であり、常に「既知」の背後には、「未知なる真理」が隠されている。「根源的信仰」もまた同様に、普遍的な人間の真理と感じられるが、実際は普遍的ではなくそれもまた相対的な真理に過ぎない。
カントの課題は「アプリオリな総合判断はいかいして可能か」に重きが置かれましたが、「普遍性と必然性」というものを、昔の時代のように神とか霊とか形而上の論理の中に置くのではなく、経験の中に見出そうとする試みです。
現代に至るずっと前、古典、聖典や偉人等の「アプリオリ的なるもの」が「普遍的な真理」とされたその「前提」は「解体」されていきましたが、しかし現代においてまだそれを「普遍的な真理という前提」と「してしまう」思考パターンは一部には濃く残存しています。
「普遍的な真理」は「アポステリオリな総合判断」とは違います。アポステリオリな総合判断は「個別の偶然性」に左右される相対的な認識です。しかし人は、「アポステリオリな総合判断」を「普遍的な真理」と錯覚したり、それを合理化して普遍化しようとする、という傾向性は引き継いでいる、ということです。
しかし、カントが「アポステリオリな総合判断」とは違うと考えた「総合命題」は、論理実証主義によって否定され、結局は「分析命題」に過ぎない、となるわけですね。偉大なカントですらドグマを抜けれない。
そして「実証主義」もまたドグマを有し、それを批判したポパーの「反証主義」では、古典や聖典、時代の常識や道徳的なるものの背景にあるドグマだけでなく、「学問的・科学的な正しさ」も同様に、「絶対不変の真理を意味しない」となるわけです。
「科学的に正しい」とは、「今現在、反証されていない」という程度の正しさになるわけですね。「反証主義」は、弁証法でも逆説でもありません。
![]() 今日の真理が、 明日否定されるかも知れない。それだからこそ、私どもは、 明日進むべき道を探しだす。(湯川秀樹)
今日の真理が、 明日否定されるかも知れない。それだからこそ、私どもは、 明日進むべき道を探しだす。(湯川秀樹)
人は何故ドグマを有するのでしょうか?それは「複雑性を複雑性のままにしておく」ということに耐えられない「わかりやすさ」への単純化、そして、「理解」の内にある知的全能感、「隠された信仰」でしょう。
理性の限界、有限性を説いたカントですら、「知的理解」の全能感を超えられず、未だ内在する「隠された信仰」「神の絶対目線」を有していた、ということです。
「内在する神の絶対目線」というのは、本人が何かの宗教の信者ということではなく、用いる概念が非宗教的であっても、本質は「自身の信じる神だけが本物」、という信仰と相似形をなしている、という意味での比喩表現です。
論理実証主義的な定義で、「検証可能性がない」「再現可能性がない」=「科学ではない」、という考え方であれば、たとえばフロイトの精神分析は科学ではありません。
しかし真理以前に、「人間」というものは一体どこにどのように存在するのか?論理実証主義的な解釈、そして公理主義にせよ、ゲーデルの「不完全性定理」によって人間理性の限界が明らかにされ、
「最初の前提」である公理に矛盾がないことを証明する(絶対に正しいとする)ことはできない、ということは明らかにされました。にも拘わらず、「最初の前提」は「個々の隠された信仰」によって「ひっそりと絶対化されている」のです。
この信仰の問題は、何かの教義を信じているという意味ではなく、「根源的な価値への信仰から生じる事実への投影」です。そしてそこに「ニンゲンなるもの」が生まれる(創造される)ということ。
そしてニンゲン自体が「虚」から生まれた、ということです。「虚」であるゆえに「実」は知りえない、ゆえに「自身の信じる価値を元にした理解」の範囲に収まるように「複雑なもの」を単純化して合理化してしまう。
「複雑なもの」が、「己が信仰の否定」にならないようにひっそりと編集され、つじつまが合うよう解釈するわけです。そうやって虚を維持し続ける創造体、それがニンゲン、ということですね。
「自身の無意識そのもの(ヒト存在)」=「実」は「何かに分割できない全体」です。ヒト存在への「優劣」の形容を生み出している主体は、「価値への信仰」であり、その本質は「虚(創造された設定)」で、
「虚」への信仰から生じた自我の運動(ニンゲン意識)に過ぎず、各々の「虚」への「根源的信仰」の違いから、「異なる信仰(価値基準)」への不寛容さが生じ、他罰性を生み出している、ということですね。
そして「何を信仰するか」は各々の「環世界」に条件づけられています。その意味で「必然」であり、根源的信仰には選択の自由はない、といえるのです。それを信じなければ価値も意味も一切の基準を失う「前提」だから、ニンゲンそれ自体が成立しなくなるのです。
ニンゲン、そして社会は「虚」に支えられている、という根源的な意味では、宗教と同様ですが、宗教とは作用する「虚」の範囲・領域が異なるんですね。
ソシュールは「コトバによって現象・世界は分節され、認知される」と考えましたが、(ソシュール以前は、唯名論、イディアが先にあるとする実念論などがありました。)
ソシュールのいうところの「※ランガージュ」(※ 音韻や概念を分節し、言語を運用する能力、身ぶり、音楽、絵、造形、踊り等、象徴化する能力)、ソシュールはそれを「人を他の動物から分ける能力」としますが、その根源にあるもの、それが「創造性」ですね。
そして「ランガージュ」が顕在化したものがラング、パロールという概念ですが、ソシュールの理論に不足したものを補う理論として、三浦つとむの「言語過程説」があります。
「言語とは何か」 より引用抜粋
言語過程説では、言語を「表現対象→認識→表現という過程(プロセス)と関係づけられた音声や文字」と定義しています。
そして、この表現対象・認識・表現のそれぞれに言語規範が結びついていることで、自分の頭の中で考えていることを他者に伝達できるようになっているのです。
ここで、言語規範は表現対象・認識・表現のそれぞれについてグループ化する作用があるので、有限の語彙や文法で無限の現象や認識を把握することができるのです。
ここで「表現対象」とは、現実に存在するものであれ、空想で考えたものであれ、客観的に捉えたときの対象を指しています。
これは言語の種類によって、何をどうグループ化するか異なっています。たとえば、鉄道の<駅>は日本語では地上を走る鉄道も地下鉄も<駅>ですが、
フランス語では地上を走る鉄道の<駅>は”gare”、地下鉄の<駅>は“station”と異なるグループ化をしています。
(中略)
次に「認識」とは「表現対象」を主観的にどう捉えるかということです。たとえば、日本では太陽の色は「赤」と考えられています。おそらく日本で幼稚園児のほぼ全員が太陽の色を塗るときに、赤いクレヨンを使うと思います。しかし、英語では”The sun is yellow.”といい、英語を母語とする子供たちは黄色い色を使います。
もし”The sun is red.”という表現をすれば、それはSF小説で赤色巨星の話をしているか、あるいは誤った認識をしているということになっています。
さらに「表現」は実際にどのような音声や文字を使って表現するかということです。これも言語の種類によってさまざまに異なっています。
(中略)
話し手(情報発信者)は、このようにして表現した音声や文字を聞き手(情報受信者)が逆に「表現→認識→表現対象」というプロセスを逆にたどることでコミュニケーションが可能になります。ただし、聞き手(情報受信者)はあくまでも、話し手(情報発信者)が表現した音声や文字を言語規範を頼りに「表現→認識→表現対象」と逆にたどっているだけなので、
話し手(情報発信者)の意図とは全く異なる内容を受け取ることがあります。また、本来言語ではないものも言語と認識する場合があります。たとえば、日本では秋の虫の音を言語として受け取ったりしています。
– 引用ここまで- (続きは下記リンクより)
引用元⇒ 言語とは何か
シニフィアン(記号表現)とシニフィエ(記号内容)には必然的な結びつきはない、これを「恣意性」と呼びます。
「真理そのものが言葉や記号で表現できる」と思っている人は、その人が「言語や観念を真理そのものと思えるほど思考が浅い、あるいは思考の質的な多元性が少ない人」なのです。
「フェルディナン・ド・ソシュール」より引用抜粋
(前略)
恣意性については「空」「縁起」などの概念で2000年前にはすでに知られていた各言語がその話者族にとって自然であると感じられるとしても、人類的には非実体的な虚構であることを示したことは、分節化の前の生きた人間の様相への問いや、東洋的な離言真如評価との接点を切り開く。恣意性を消し去る高度な技法が釈迦によって発見され、実践体系や生き様にまで高められた。「空」の概念は原語のサンスクリットでは「シューニャ」と元々呼ばれている。”恣意的な関係性”の概念「シーニュ」「シーニュ」の概念が、言語に限らず様々な象徴や指標でも見出される
– 引用ここまで- (続きは下記リンクより)
引用元⇒ フェルディナン・ド・ソシュール
「根源的信仰」から生まれる行為も、「前提」からの必然的な反応であり、(根源的に)選択の自由によるものではない、といえます。
自身の信じる価値を「正しい」とする前提がある故に、「価値があるもの」と思っているがゆえに、自他を肯定したり否定するジャッジができるわけです。「根源的信仰へ向かわせる力」は必然性、本質的なものですが、「価値」「意味」は相対的であり「構築されたもの」です。
では「根源的な何かを知らないままそれとの対面を拒否する」のはダメなことでしょうか? 「普遍的真理ではないものを普遍的と思い込む人間の錯覚」はダメなのでしょうか?といえば「いいえ、それでいい」と私は考えます。(ただ極端になりすぎないバランスは必要です)
「真理」は常に隠されています、何故ならそれは「意識」を超えたもの、だからです。五年ほど前の過去記事でも少しこのテーマに触れ、その時にTEDの動画も紹介しましたが、
〇 認知科学・脳科学でみる認知の進化と発達 再構築される心の現実
今回再び紹介です、「認知科学者のドナルド・ホッフマン」のTED動画で、「認知科学・脳科学でみる認知の進化と発達 再構築される心の現実」です。
![]() 現実を全く見ることなく ただ適応していくものだけが 現実をあるがままに見る生物を絶滅に追いやる (認知科学者 ドナルド・ホッフマン)
現実を全く見ることなく ただ適応していくものだけが 現実をあるがままに見る生物を絶滅に追いやる (認知科学者 ドナルド・ホッフマン)
「ドナルド・ホフマン: 我々には現実がありのままに見えているのか?」
現実を全く見ることなく ただ適応していくものだけが 現実をあるがままに見る生物を絶滅に追いやるのです
最低限 言えることは進化は縦断的な もしくは正確な知覚を求めていないのです 現実を知覚することは絶滅へと導きます
これはちょっとした驚きです世界を正確に見ないことが 生存する上で 優位性があるのは なぜでしょうか?
(中略)
我々は現実をあるがままには見ません 我々は生存を可能にするために現実を異なる表現で知覚しているのです それでもなお我々は直感に頼ることが必要です 現実をあるがままに知覚することが なぜ有益ではないのでしょうか?
(中略)
知覚は誤解されていました 時空と物体は あるがままの現実であると信じています 進化論はまたもや我々が間違っているのだと主張します 我々は知覚による体験を誤って解釈しているのです我々が目で見なくても存在している何かがありますが それは時空でも物理的な物体でもありません
(中略)
脳ないしニューロンによって知覚的な体験をするとき 現実との作用が働きますが 現実は脳やニューロンによって構築されたものではなく 脳やニューロンの構築物とは全く異なったものです
![]() 進化は縦断的な もしくは正確な知覚を求めていないのです 現実を知覚することは絶滅へと導きます
進化は縦断的な もしくは正確な知覚を求めていないのです 現実を知覚することは絶滅へと導きます
「絶滅へと導きます」という表現はよく合っているでしょう。ただ表現を変えれば、それが「根源的なものを悟る」ということで、本来「根源的な悟り」は非ニンゲン的で、非宗教的なことです。
つまり、「信仰」というものの本質は宗教にあるのではなく、人間においては現実の認識が既に信仰であり、信仰から始まる世界に生きている、ともいえるわけです。
事実判断ですら、厳密にはそれが事実そのもの(現実)かどうかはわからない再構築されたものとはいっても、人間の意識・思考の範囲では客観的事実といっても問題はないわけですが、
価値判断であればそれは人類にとって相対的なものなので、普遍的ではありません。「その価値を信仰している一部の人間」にとって「真理だと思えるもの」なんですね。
「存在を根底から支えているもの」に触れるというのは、ニンゲン意識ではなく意識の根底にあるヒト、生命の無意識が触れるのであり、それ自体は一切の言語、前言語的な理解の過程の中にはない。
よって「それ自体」が語られることはありえず、それは永遠に語られないものなのですね。