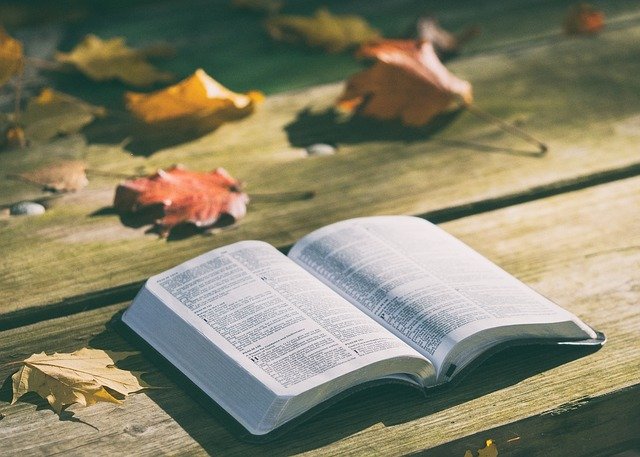![]() 人間とか実存とかいうことは、それに関連する諸問題と合わせて、哲学の最も重要な問題であると私は考えている(九鬼周造)
人間とか実存とかいうことは、それに関連する諸問題と合わせて、哲学の最も重要な問題であると私は考えている(九鬼周造)
今回は「ミーム的進化」がテーマの記事で、わかりやすい例としてキリスト教を中心に、他の哲学・思想を少し含めて書いています。前回のテーマのロゴス的知性のジレンマの補足の記事でもあります。
やはり「言語」そして「コトバ」というのは大事です、いえ魔力そのものでしょう。ではここでまず一曲、これぞ言葉のプロですね(笑)気に入りました♪
何故今キリスト教なのか?キリスト教はもはや近代の主要なミームではありません。しかし、無意識(基層のミーム)は近代的自我(主に西洋)に引き継がれているのです。そして深層において、世界で生じている運動、社会問題やアイデンティティの問題とも被るテーマだからです。
増加する若者のカトリック教会離れ-米国の調査結果(Crux)
この調査をもとにした分析によると、教会から離れる原因は大きく分けて六つある。教会のある儀式あるいは一連の儀式への疑問、文化的な世俗化の進展、信仰を捨てた後にくる新たな自由の感覚、強制されて信じ込まされた信仰の拒否、宗教を持たずに倫理的な生活ができるという確信、道理にかなった議論や証拠を示されたことで起こる信仰を再評価する意欲-だ。
文化には表層文化と基層文化という分類がありますが、「身体性」というものを含めている場合は、「基層文化」の方にウエイトを置いています。(これに関しては記事の後の方で書いています)ではここで、宗教学者の中村 圭志氏の記事の引用紹介です。
「世界のどの宗教にも共通する3つの大事な役割」 より引用抜粋
神学の究極的説明は、あくまで個人個人の気持ちを納得させるためのものです。ですから究極的と言いつつ、状況に応じて論点をズラしていく――言い訳を重ねる――のが常です。
例えば神に祈れば病気が治ると言います。しかし治らない。そこで「病気は神の試練です」とロジックを変えます。
また、悟れば人生の問題は解決すると言います。しかしいくら坐禅しても人生の問題は晴れない。そこで「真の悟りはブッダのみにある」とロジックを変えます。
言い訳というと聞こえが悪いのですが、こうした知的操作を重ねることで、信者は人生の奥深さに目覚めていくことができます。人生には裏があり、裏にはまた裏がある……この経験的事実を、神学もまた教えてくれるのです。
しかしまた、こうしたロジックになじむことによって、信者はどんどん思考の深みに引っ張り込まれ、人生の解決というよりも自問自答に一生を費やすことになります。このような探求に興味を抱くのは、一部の信者――リクツの好きな信者――に限られるでしょうが、そうしたエリート信者が聖職者や神学者になることで、宗教は次世代に伝えられます。- 引用ここまで- (続きは下記リンクより)
「この一節ではこうあります、この箇所にはこう書いてあります」みたいなやりとりは、彼等と話すときによく出てくるもので、たとえば神学で論を立てる側はそれが演繹法のつもりでしょうが、いわゆる「ロゴス的知性のレトリック」の部類なんですね。
まぁ上の文中では「言い訳を重ねる」と書いていますが、単純に言えばそういうことです。科学でも様々な理論がありますが、「科学的に一つのことを証明する」というのは、そういうやり方は通用しないんです。
本来、キリスト教の思考の型、原理はカルト性を強く帯びているのです。逆説的ですがそれが「力」だったんですね。排他性、分離性ゆえに力があったわけです。世俗化するというのは「聖なるもの」と「俗なるもの」の境界がなくなっていくことであり、
「価値として差別化されているから存在しているもの」を世俗基準で価値相対化すれば、聖なるものの差別化が取り払われて無価値化されていくのです。権威、パターナリズムの脱構築化、そして価値相対主義によって大きな物語は崩壊していく。
では再び宗教学者の中村 圭志氏の記事の引用紹介です。
「宗教がわかってない人はこの4原則を知らない」 より引用抜粋
「多神教、一神教それぞれの美点と欠点」
一神教は、多神教の神々を否定する形で発達してきました。諸民族の奉じるさまざまな神々はぜんぶ幻だ、というのが一神教の主張です。ユダヤ教もキリスト教もイスラム教も原理的にはたいへん排他的です。一神教の神は唯我独尊の派生・影響です。
一神教にはジレンマがあります。万人の上に立つのが唯一神ですから、万人はこの神の前に平等とされます。しかし、その神を信じない人に対しては「真理に背くヤツ」ということで批判的な目を向けます。だから、事実上、「信者 vs. 異教徒」という差別意識が現れるのです。
「平等だ、愛だ、平和だ」と唱えつつ、異教徒の弾圧を行う――そういう悪い癖が一神教にはあります。これに対して、多神教は通例、ほかの民族の宗教に対して寛容です。神々が多いのに慣れていますから、民族Aの神々と民族Bの神々は容易にごっちゃになってしまいます。- 引用ここまで- (続きは下記リンクより)
◇ 他・関連記事の紹介
〇 戦争と文化(17)――聖書には「汝、殺すなかれ」とあるのに、どうして、ユダヤ=キリスト教は戦争や暴力行為を後押ししてきたのか?
過去に多くのカルトや原理主義的思想の人々と会ってきましたが、「思想を受け入れない人や批判する人」に対して「地獄に堕ちる」と言ったり、他にもまぁ大体同じようなことを言う人は一定数いましたが、カルト信者でもすべてがそんな他罰的な不寛容な言動をするわけではなかったです。個人差はあります。
しかし「傾向性」はある、そういうものの背景を観ていく、という文脈ですね。
とはいっても「弱小零細カルト」と比べれば、遥かに巨大な伝統宗教の方が過去には凄い残酷なことを異教徒や異端に対して膨大なスケールで行っていたのです。現代においても伝統宗教の一部に残存していますし、まぁ思想やそれに基づく運動や信仰等で極端になってしまうタイプの人は「宗教に限らず」一定数います。
そういう傾向は「バイアスと防衛機制の組み合わせ」次第では誰でもなりえるのです、また「悪の凡庸さ」という有名な言葉もそうですが、よく目立つ病的な人だけが極端なことをするわけではありません。なので他人事だとは思わずに反面教師にしていく姿勢は大事です。
自己統合がシッカリしている人でも、何らかのキッカケで退行し変性意識状態に入ると、一気に人が変わったように異常になっていく、そういうガラッと変わってしまう例を現実で観てきました。「あのシッカリした人がこうなるのか」というほどあっけなく変わってしまいます。
ある種の条件が重なると、深い意識での同化一体化には、そういう怖さがあるんですね。そのあたりの危険性を考慮し、過去に様々な角度から記事を書いてきました。主に精神分析、精神医学、脳科学、心理学の概念で考察してきましたが、
病的な変性意識状態に関しては脳科学だけでなく、「自己愛」(このブログでの「自己愛」に対する捉え方はコフートが近いです)、ユングの元型の概念や精神分析の防衛機制の概念等を使っていますが、
「無意識が投影されたものとしての神」の内的経験は十代後半~二十代前半の頃の体験から生じた観察と分析ですが、大きなくくりで「虚の創造性」のひとつの現れです。そして無意識には個人的なものと集合的なものがあります。
ところで脳科学、心理学、精神分析だけでなく、この方面でとても深い観察だなぁと感じたのは精神科医の中井久夫氏ですね。「医療人類学」での視点は特に面白いです。
中井久夫氏はその道の専門家ですが、専門的な概念をただそのまま受け入れるのではなく、それ以前の背景「文化」を観ていく、という姿勢、考察の幅と、知見の豊かさが凄いんですね。
こんな精神科医がいたのかぁ、と本を読んだ当時はビックリでした。
精神科医の中井久夫氏の著書「治療文化論」では、天理教教祖「中山みき」のことが書かれていますが、どのようにして「教祖」が誕生するのか?の文化的背景の分析が面白いんです。そして「精神疾患は文化が作り出す」という人類学的視点もそうですが、現代精神医学的なものとは全く視点が違うのです。
参考論文をひとつ紹介しておきます ⇒ 信じるということ~精神疾患にみる宗教性
個人的には中井久夫氏の捉え方は共感するところは多いのですが、内的な体験としての視点から、それだけでは説明がつかないことがあるのです。そういう部分にはもっと個別的な差異があるのでしょう。
こういう分析は、私の中では十代後半からスタートした考察なんですが、ブログに関しては内的な体験のほんの一部のみしか書いていません。
残念ながら2000年代になってもまだカルトに騙されるような人がいるのです。それ以前の年代にハマった人は、まだ世間はオカルトブーム全盛期だったので、霊能やカルト系新興宗教にハマるのは、ある部分はメディアの責任もあるでしょう。
著名な宗教学者ですらオウムや他のカルトの本質を正確に見抜けていなかった人が結構いた時代です。まして一般人は宗教を俯瞰する力などなかったでしょう。しかし身体知の深い人は一瞬で見抜いていましたね、それは「専門・非専門に関係のない知」だからです。
感性的なもの、それ自体を感じる力、と概念知は異なるので、体系的な知識がそれほど役に立たないことがあるわけです。身体知の方が一瞬で見抜くことは意外に多いのです。
シンプルな話をすると、あるイメージを言葉にするとき、不可避に情報圧縮がなされる。その情報をそのまま解凍するには、同じ体験をしていなければならない。では、同じ体験は可能か? と考えただけで、言葉に慎重になれる。但し、言葉でしか考えたことがない人には、このシンプルな話すらわからない。
— 中島 智 (@nakashima001) April 8, 2021
深い身体知を持つ人は、それだけ切実な理由や状況、強烈な体験、現実との関りがあってそれを観続けている人なのです。アカデミックな知とは全く異なる視点を与えてくれるものが身体知です。
しかし「当事者の知恵」等は専門家に否定的に言われることも結構見聞きします。特定の学術的な文脈で観れば問題点を発見するのは簡単でしょうが、
それを差し引いても非常に多くの知恵が含まれていることがあり、専門知では補えないローカルさの中には、身体知でしか知りえないものが多々含まれるので、その個別性の深みはとても面白いです。
ローカルな知は、その場・状況の中で行動し生きる人の身体知なので、膨大な個別性の知でありながら、その多くは体系化されないことが多く、「その場(現場)でしか得られない」という基本性質があります。
ずっと考えてることについて書いてもらうと面白い。これは世の真実で、たとえば学校がどんなところか語ってもらうなら、劣等生がいい。優等生がサラッと通り過ぎるところに、劣等生は学校全体の宿痾を見出す。つまり、意識的にワザワザ考えたことの10倍、無意識的に考えざるを得ないことの方が面白い。
— 東畑 開人 (@ktowhata) April 2, 2021
諸民族の神話が形成される条件として、心理的内的要因である「神話素」、これはユングの元型のことであり、社会的要因としては「生の様式」が条件で、これは基層文化に含まれるものですね。⇒ 日本人の個人的影と集合的影を読む
「世界のどの宗教にも共通する3つの大事な役割」 より引用抜粋
文化の基層として
社会が科学の成果を大々的に取り入れるようになってまだ数世紀もたっていません。宗教は思想、語彙、習慣の形で文化の基層を成しています。
日本人は仏教の教理を大方忘れていますが、それでも欧米人に比べたら仏教的あるいは儒教的な発想法をもっています(修行・修業を強調し、世界を建設的というよりも無常観で眺める傾向があり、先輩後輩などの序列を重んじる、など)。
欧米人の中にはもはや教会に行かない人も多いのですが、しばしばキリスト教的なところを見せつけます(慈善を重んじ、キリスト教の終末待望を受け継ぐ、未来のユートピア建設への希望をもっている、など)。
基層文化というのは侮れない力をもっているからこそ、個人的には無宗教だと思っている人々も、宗教の歴史や教えを教養的に学ぶ意味があるわけです。
– 引用ここまで- (続きは下記リンクより)
引用元⇒ 「世界のどの宗教にも共通する3つの大事な役割」
キリスト教は変化しつつ枝分かれして多元的なものになっていったとはいえ、原初的なミームの型でいえば、イスラム教、ユダヤ教と同じ元型を共有していますが、元型は一つだけではありません。よってそれぞれに元型的個性があります。
仏教も様々な国で独自に進化し、哲学体系も多元的です。しかし仏教は仏教の、キリスト教はキリスト教の元型を共有し、基層のミームは集合的無意識で繋がっているのです。
どんな宗教も何かの元型は共有しているので「要素において似たところがある」、しかしそれを「宗教は根源的には一つ」と錯覚する人もいますが、同じではありません。しかしニンゲンの創造性が生み出す、という意味で根源的な源泉は同じです。
文化や思想を生み出す元型、そして原初の思考の型がありますが、表現型は多様でも、無意識のルーツは繋がっている、それがミーム型進化の系統樹であり、そこには幾つかの質の異なる原初の型があります。
表現型の枝葉末節をみればいろいろありますが、根は繋がっている、その根の質を観る、ということですね。「スポットをどこに当てているか」の違い、それが「同じ分野の学者によっても見解は異なる」という見解の多様性を生じさせます。しかしそれぞれに「その文脈において」意味があるひとつの見解なのです。
カルト、イデオロギー、思想等で単一の価値を絶対化する人が、教条主義化、原理主義化していく度合いに比例して排他的になっていく構造において、思想の元になっている原初の思考の型、そして観念を枠組む元型の質は大きな作用をもたらします。
それは元型が「無意識領域の力動の作用点」になっているからで、基層で自我意識に強い力を与えるのです。それが文化の根源的な力であり、ある種の「マナ」を持つのはその力の作用です。
これは単にユングの元型の概念を使って考えただけではなく、ユングの概念以前に、十代後半~二十代前半の頃に実際に意識内に現象化したことをわかりやすく伝えるために、昔からよく知られたユング等の概念を使って、多くの人が「イメージしやすいように」書いているだけなのです。
「状態」によって作用は変化するものです。高次の防衛機制が働いている状態では極端な作用は生じにくく、病的な状態というのは低次の防衛機制が優位になっている状態であり、もっと極端になると原始的防衛機制の状態です。
また無意識の感性領域の「内的体験」は言語化できないものが多く含まれているので、何かを語ったとしても、結局のところ「言葉に現れていないもの」「言語化できないもの」は本質的に変わらないままなのですが、
創造性もそうですが、それ自体は専門、非専門は関係なく、身を通した知の方に実体があるのです。こういう話は身体を通して理解していく専門家や芸術家の方は深く理解されている方が結構いますが、そうでもない学者も割といます。この種の知はアカデミックな権威に独占できない。哲学も本質はそういうものだと思います。
哲学の英語はフィロソフィーで、「知を愛する」という意味だというのは有名な話。「愛知」(まるで地名みたいだけど)の観点からすれば、知がどんな分野、どんな人間から語られようと、面白いものは面白く、愛すべき知。
— shinshinohara (@ShinShinohara) October 17, 2020
逆説的ですが、ある種のカルト性、過剰なタブー、無意識の力、それこそが宗教の力ともいえるのです。よってカルト信者の言い分はある範囲に限定すれば「正しい」ともいえます(笑) 「文化にすらなれない弱小零細カルト」が世俗化(寛容化)し無意識が意識化されてしまうと、それはあっというまに消え去ってしまうでしょう。
多くの人々はそれを望んでいますが、信者からすれば徹底抗戦したくなるのも当然でしょう。
強力なカルト性+政治性で発展した巨大なキリスト教ですら、世俗化と意識化で緩やかな解体にむかっていく流れにあるのですから。その意味でイスラム教は最強でしょう。巨大で在りつつ今も「排他性・不寛容・無意識」を徹底しています、世俗に妥協しません。
あれぞキングオブ宗教であり本来の宗教の在り方なのです。
以下に紹介の外部サイト記事では、「こころ教」という表現が出てきます。これは言い方を換えれば「集合的無意識の力(マナ)を失った信仰形態」のひとつなんですね。「原理主義」に向かうほど集合的無意識の持つマナは強くなるのです。
また同文中において、宗教の中の「律法主義」的な側面と「霊性主義(スピリチュアリズム)」的な側面という二つの側面から宗教を考察しています。
アラブ世界でも、イスラーム世界一般でも、「こころ教」化は進んでいない。(中略)圧倒的多数は、人間の外部に神が絶対的な規範を定め、それを人間は護持していく義務があるのだ、と信じている。その意味では、イスラーム教徒の大部分は、ここで「こころ教」と対比されている「原理主義」的な信仰を維持している。
皮肉なことですが、カルト的な排他性から寛容に向かったゆえに力を失ったキリスト教は、「ミームの力」という視点から観れば、もはや神界から破門されるべき世俗に堕ちた一般大衆文化程度の力しかないのです。
弱小零細カルトはキングオブ宗教になりたくてもなれないでしょう。大きな物事の達成には、時期とタイミングと「場」と「人」との関係性、それ等が全て揃うこと、そして生み出すものには「中心力」の強さが必要で、簡単なものではないからです。まして千年以上も続くような文化となるものは並大抵の力ではないのです。
あるべき排他性
「悪」という概念は存在に対する排他性であり、存在の「価値」の区分けであり差別化なんですね。善悪の価値基準、これは排他性なくしては生まれないのです。根源的には、「概念そのもの」が既に排他性をもっています。
「あるべき排他性」というのは、人間社会は元々「排他性」なくしては維持できず、また根源的には生物はみな「境界」を有し、自と他(非自己)の区別、中心性と排他性で個体を維持しています。よって生命に必要なものである、ということです。
人間社会というものは、ヒトと動物を分け、悪人と善人を分け、良い事と悪い事を分けることなしには成立しません。「分離性」が必要なのです。「分別」というのは排他性を含んでおり、「人間みんなちがってみんな排他的」も人間の自然な一面なのです。
「聖なるもの」と「世俗」を分けるのも分離性であり、排他性なのです。なので人間の歴史において、キリスト教の原理の性質である「分離性が非常に強く排他性が非常に強い作用」を世界に与えてきたのは、ヒトの「創造・維持・破壊」のサイクルにおいて、創造の過程での大きな役割を果たしていた、ともいえるのです。
現在はその大きなミームの役割を終えたので、「破壊」の末期、ミームの衰退へ向かい、形骸化・世俗化した文化となった。
そして理性・ロゴス的知性は「大きな物語としての神」を殺しましたが、本当は死んではいないのです。恐竜は絶滅しましたが、実際は鳥の姿に進化し生き残っているように、姿を変えてミクロな神は今も生きているのです。
スピ、精神世界も枝葉末節を見ればいろいろ分化していますが、「自己宗教」という大きなくくりでみれば宗教の一種であり、ミーム的進化の系統樹で枝分かれして生じてきたもののひとつです。啓蒙主義もそのひとつの進化系です。
「アメリカにおける個人主義とニューエイジ運動」 より引用抜粋
一般に、宗教は近代化が進むにつれて衰退していくものだと見なされており、現代は「世俗化jした時代である、と考えられている。宗教社会学においても、調査によって教会出席率や洗礼率の低下が確かめられるようになり、そうした現象を説明するために 1960年代から「世俗化(secularization)」という概念が使われるようになった。
しかし、「世俗化=宗教の衰退jという図式は、全ての学者に受け容れられたわけではない。当時のそのような通説に異議を唱えた代表的な研究としては、トーマス・ルックマンの『見えない宗教』(1967)が挙げられる。教会や教団などの「目に見える宗教jは衰退したが、個人の内面にある「目に見えない宗教jは現代でも残っている、とルックマンは主張した(Luckmann1967=1976)。
それを受けて他の宗教杜会学者のあいだでも、宗教は公的領域にあってはその影響力を縮小させているが、私的領域にあっては必ずしもそうではない、という考え方が広まっていくことになる
– 引用ここまで- (続きは下記リンクより)
上の文中に出てくる『見えない宗教』、これもミームです。「ミクロな神」は「ナラティブ化した現代の個人の無意識」にも存在し、それが分離肥大化して自己神化が現象化すると、少し前なら新興宗教の教祖やカルト教祖になったり、独裁的な人物になったりするパターンが多かったのですが、
大きなミームが失われ元型の力の弱まった個人主義化した現代社会では、もっとスケールの小さな自己神化現象が生じています。しかし集団化することである種のカルト集団のような力学を生み出し、多種多様な神クラスターが勃発しています。
まるで「皆が神になりたがっている」かのようです。モンスターエンジンの「私は神だ」なら笑えますが、
そうではなくナラティブ化した神々は正義の剣を振りかざし聖戦を繰り広げ始め、まるで時代は変わっても中世に逆戻りしたかのような退行現象が確認されます。神の数こそ多いですが個々のスケールは小さくミジンコエンジンなのです。
新約聖書にある「復讐するは我にあり」、この「我」とは「神」の意味ですが、自己神化した者たちは、「個人の心が神」なので、絶対正義化し「復讐するは我(自分)にあり」になっているのですね。その意味で個人でありながら徹底した断罪性を生み出す力学になりえるのです。
啓蒙主義の中にも「ミクロな神」は存在し、絶対化された理性によって神目線の裁きを「野蛮・無知とされた対象」に対して加えます。そのやり方もキリスト教的で、異文化圏に強く干渉し変化を強制し、彼らの絶対基準で啓蒙して支配統一する、しようとするのですね。その意味ではポリコレも神の意志なのです(笑)
そして啓蒙運動をする人の精神状態も多元的で、バイアスと防衛機制の組み合わせ次第では、かなり病的な状態になる人も一定数存在し、過去の異端審問の残酷さの再現のような光景になるのです。
近代的自我は、宗教という先祖的ミームの進化型で、「根源的な意味」では宗教と別物ではなく、合理的で近代的な個人も「進化型ミームという大きな宗教」の信仰者です。そして「虚」の創造性は「創造・維持・破壊」のサイクルを経ながら進化・変化していきます。
ニンゲンの虚の創造性のひとつである神に限らず、それ以外のあらゆる創造性そのものが本質は「虚」ですが、キリスト教の面白いところは、自らが鍛え磨き上げたロゴスによって、ニンゲンの「価値」「意味」における虚の創造性を高め、それが「人権」という概念を生み出す力学になったり、
またロゴス的知性の昇華による西洋科学の発達にも繋がっている、というところです。自らが生み出したニンゲンの理知の過剰さと昇華によって、逆に自らが見切られ、理性の刃物で自殺するかのように「神を殺した」、そうして「虚の創造性の破壊」の過程に向かっていったのです。
しかし神は死んでいませんでした。ひとつの大きな神の物語が死んだだけなのです。恐竜が鳥に進化するように。
宗教は思考の型だけを見れば単純でとてもわかりやすいですが、世界は宗教のロゴスでは全く理解できない未知・新しいものに溢れています。
しかし「基層のルーツを絶つ」というのは根なし草になります。アイデンティティポリティクスの問題も無意識の目線ではここに繋がっている、ともいえるでしょう。
グローバル化した現代社会で、個々の依って立つ共同体、そして基層のミーム、元型の力を失い、自我の支えが脆弱にある状態だからこそ、共通の基盤を失った個人は実存的不安を強化しやすく、アイデンティティの危機からアイデンティティポリティクスが過剰になってくる、という力学です。
その中には自我拡散し退行し低次の防衛機制が優位になった者も含まれ、それらの意識が集合すると運動は極端化、カルト化するのです。しかしこれは「無意識の衝動」であるため、非常に強い力が背後にあるのです。
無意識は自と他の区別がない、基層が自他未分離で融合しているのです。「意識せずに支えられている」という土台、それは自我を安定させ、そして共同幻想を有する共同体内で個が包摂されるとき、「場」は自我を保護する力にもなっていたのです。
信仰の逆説と既知から未知へ
「神」へと向かえば「自己」に至る、その逆説は、「自己」へ向かえば「神」に至る、それはいずれも閉じた世界の自己完結。そして「他者」へ「人」へと向かう、この他者・世界との関係性を通じて「神」を知る時、世界は開いていく、全体性から無限へ。
レヴィナスの語る「他者論」にもその視点が含まれていますが、レヴィナスの自我観は「自分以外のもの」に根拠を持つのではなく、自分それ自体に根拠を持っている。
ところでレヴィナスの思想の背景にあるミームは何か?といえば、ユダヤ教のミームであり、その元型・思考の型から新たな思想をクリエイトした人ともいえます。単純にユダヤ教思想家ではないです。
![]() 生きているという単純な事実によって、私たちはすでに幸福のうちにある(レヴィナス)
生きているという単純な事実によって、私たちはすでに幸福のうちにある(レヴィナス)
レヴィナスは、神学、特にキリスト教神学は、神を存在者の次元に貶めながら、神を考察しようとしてきたと考える。そしてその意味で、キリスト教神学は、哲学の支配に屈しているのである。⇒ レヴィナスにおける哲学と宗教
これは私も同様に考えます。ゆえにキリスト教神学は哲学を超えられない。そして哲学はもっと広く深くその先へと向かっていく。
「レヴィナスにおける哲学と宗教」 より引用抜粋
レヴィナスは宗教の思考において、神を〈経験〉の一つの主題として考え始めると、必ず哲学の領域に転落してしまうと考える。人間の経験の可能性の条件を考察したドイツ観念論からフッサールの現象学にいたる強靭な思考のパターンを逃れることはできなくなるのである。そこでレヴィナスが提示するのが、「無限」の観念である。
当然ながら、ドイツ観念論以来、無限の観念は重要なテーマとして考察されてきた。しかしレヴィナスがここで提示する無限の観念とは、こうした哲学的な主題としての無限の概念ではなく、こうした考察をつねに乗り越えていく運動としての無限の観念である。
(中略)
神は意識の志向性によっては認識できないものであり、しかも人間の意識のうちにこの観念が内在しているということに、神と無限の観念の特異性があるとレヴィナスは考える。デカルトはそれが意識に「生得的に」含まれると考えたが、レヴィナスはこの概念が意識に刻印されているということの受動性の契機を重視する。この受動性とは、カントが感性に与えた受動性とは異なるものとして考えられている。カントは人間の有限性とは、感性が存在者によって「触発」されなければ認識できないことにあると考えていた。
– 引用ここまで- (続きは下記リンクより)
引用元⇒ レヴィナスにおける哲学と宗教
「レヴィナスにおける主体について」 より引用抜粋
レヴィナスの思想において《他》という原理は、主体の変容をとおして徐々に明らかにされていく。《他》が原理であるということは、具体的な他人との関係における主体の変容をとおして論じられているのである。
それゆえ、あくまで目の前の他人との具体的関係が起点となっているのであり、レヴィナスの思想は他人そのものの個別性を否定することを目的としているのではない。
また、主体の変容をとおして《他》を語るという方法は、《他》自体については語ることができないというレヴィナスの思想の特徴上、必然的に決まってくるものでもある。《他》そのものについて語ることはできないため、主体の側の変容として語るしかないのである。
それゆえ、レヴィナスの他者論、あるいは《他》という原理から組み立てられる倫理は、必然的に主体の側の記述、すなわち自我論となる。
– 引用ここまで- (続きは下記リンクより)
引用元⇒ レヴィナスにおける主体について
ところで、デリダが「暴力と形而上学」においてレヴィナスを批判しましたが、デリダの用いる「超越論的暴力」や「ロゴス中心主義」という表現は、前回の記事で書いた「ロゴス的知性のジレンマ」とも関連するテーマです。
ジャック・デリダによれば、西洋哲学の歴史は、最高の真理にまで至る「意味」がロゴスのうちに宿るとする「ロゴス中心主義」によって支配されてきた。それは声のうちに主体の意図する意味が直接的に現前するとみなす「音声中心主義」と結びついており、存在の意味を現在における現前とみなす「現前の形而上学」に基づいている。
デリダによれば「表音的-アルファベット的文字と結びついた言語体系」において「存在の意味を現前と規定するロゴス中心主義的形而上学」が生み出されたのであり(DG64/89)、ロゴス中心主義は西洋の自民族中心主義でもある。⇒ 脱構築と自民族中心主義
思考することとは自己が語るのを聴くことであり、「自己への現前」であった。(中略)このような「自己への現前」においては現前を可能にしながらも、自らは現前しないものが忘却されてしまう。デリダはこのような事態をロゴス中心主義=音声中心主義と規定し、これを批判していた ⇒ 声と言葉
レヴィナスの「ロゴスで思考された他者」ではなく、そして「無限の観念」によるのでもなく、「無心、無為自然」は、概念以前の世界へと開いていくことであり、その時初めて「未知」「常に新しいもの」と出逢う。「既知なる概念」ではない「未知なる体験」に出逢うのです。
「天と地と人」が調和するというのは、天に偏らず、地にも偏らず、人にも偏らず、そのいずれとも対立的関係を持たない調和、そこに自生するとき、虚と実の創造性も自ずと調和する、ということです。